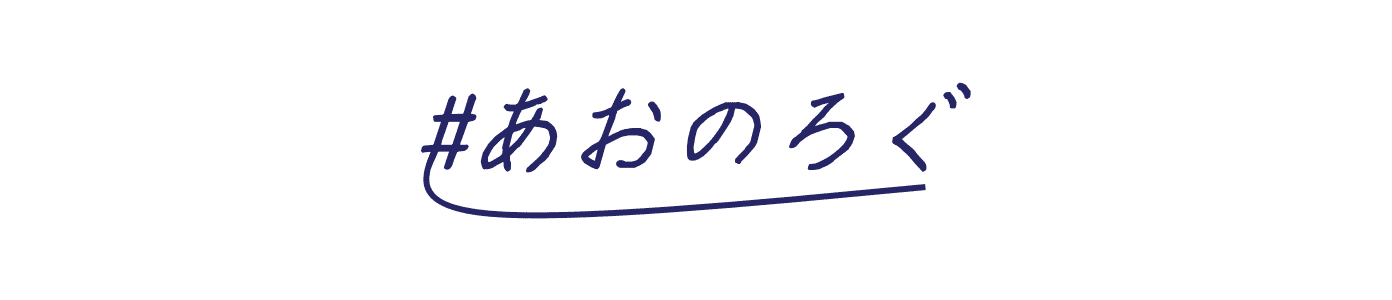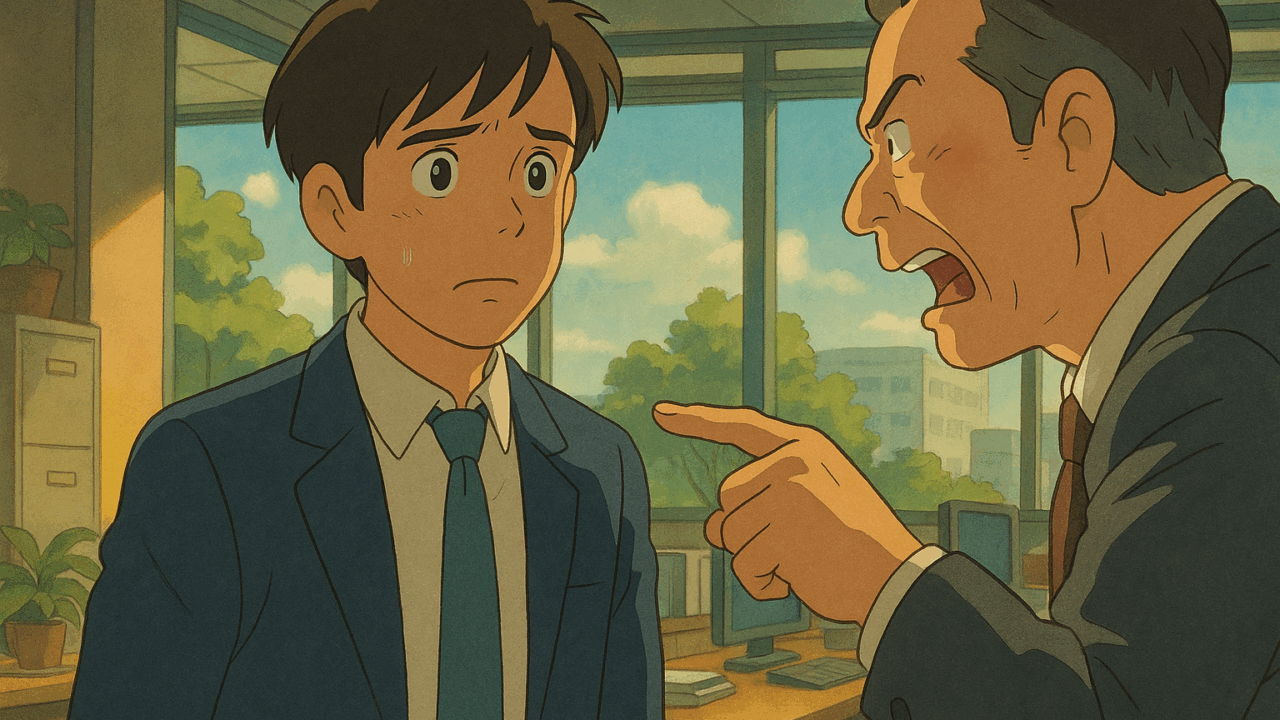「上司に『こんなこともできないの』と言われたらどうすればいいの?」
「こんなこともできないのって言ってくる上司の心理って何?」
「こんなこともできないのでメンタルが落ち込む理由が知りたい…」
世の中にはなんでそんな言い方するの?っていう上司がいますよね。
かくいう僕も上司に「こんなこともできないの?」と言われたことのある1人です。
やっぱりものすごくショックを受けたのですが、のちのち「なんでこの人はそんなこと言うんだろう?」と気持ちが湧き上がり、最終的には「なんやねん、この上司!」と思っていました。笑
そこで今回の記事では僕の実体験も含めて、
- 「こんなこともできないの」と言われたらどうする?
- 「こんなこともできないの」と言ってくる上司の心理5選
- 「こんなこともできないの」でメンタルが落ち込んでしまう理由
- 「こんなこともできないの」と言われた時の対処法
について1つずつ丁寧に解説していきます。
「こんなこともできないの」と言われたら
まず最初に結論ですが「こんなこともできないの」と言われた時、自分に矢印を向けるのはやめましょう。
世の中「自己責任が大事。他責にするな」と常々言われますが、個人的には、メンタルがやられてしまうくらいであれば、どんどん他責にしちゃっていいかなと思ってます。
もちろんやりすぎはよくないけど、上司から言われた言葉をしっかり受け止めて、悩みに悩んで、この記事に辿り着いたあなたは、きっと素敵な方なんだろうなと思うので、今日くらいは他責にしちゃってください。笑
自分を責めすぎるのもよくありません。
優しすぎるあなたは一旦ここでゆっくりと休んでいってくださいね。
てめーが新人の頃はどうだったんだというスタンスでいよう
これ学生でアルバイトをしていた頃によく思っていたことなのですが、無駄に新人に厳しい先輩とかいませんでしたか?
「そんなところ突っ立ってないで自分で仕事探したら?」とか「そこで何やってんの?邪魔!」とか、、(まぁ単に自分の仕事ぶりが悪かったと言うのもありますが…)
僕も最初の頃はものすごく反省していたのですが、途中から「お前どやねん?」「てめーが新人の頃はどうだったんだ」って思ってました。笑
すると少しは楽になるんですよね。
新人と上司のレベルを比較すれば、そりゃ上司の方がレベルが高いのは当たり前です。
だから見たことはないけれども、今の自分と昔の上司を比べることが大事なんです。
誰だって新人の頃は何もできなかったはずです。
また新人の頃からなんでもできた人しごでき人間は「こんなこともできないの」なんて、時代錯誤なセリフを吐いたりしません。
つまり、こんな言葉を言ってくる時点でしごでき人間じゃないんです。
だから「こんなこともできないの」と言われたら「てめーが新人の頃はどうだったんだ」というスタンスでいるようにしましょう。
「こんなこともできないの」と言ってくる上司の心理4選
それではここから「こんなこともできないの」と言ってくる上司の心理について見ていきましょう。
上司の心理をすることで、少しは気も楽になるかと思いますので、ぜひゆっくり読み進めて見てくださいね。
またこの章では
- あなたに対してマウントを取りたいだけかも
- 期待値と現実のギャップにイライラしている
- あえてプレッシャーをかけてくる
- 作戦ただのストレス発散で言っているだけ
この5つの心理について1つずつ丁寧に解説していきます。
あなたに対してマウントを取りたいだけかも
まずは「マウントを取りたいだけかも」という心理についてです。
つまり、上司の言っていることは大して中身があるわけではなく「自分の方が上だ」と確認したいだけってことです。
新人と上司を比べた場合、仕事ができるのはもちろん上司ですし、経験値もスキルも高いです。
だからマウントがとっても取りやすい立場という関係性なんです。
これって大人が赤ちゃんに向かって「まだ立てないの?まだ喋れないの?」とか言ってるようなもんです。笑
赤ちゃん側からしたら「いや、今できないのでは当たり前でしょ!!」って話なんですが、あえてこの言葉を言って、できないことを突いて優位に立つことで、上司は安心感や満足感を得ているってわけです。
ただ、こうしたやりとりの裏には「自己肯定感の低さや不安の裏返し」が隠れていたりすることも少なくありません。
つまり、部下にマウントを取ってでも「自分は価値がある」と感じたいってことです。
なので、もし上司にこの言葉を言われた時は「ああ、この人は今自分を大きく見せたい時なんだな」と寛大な心で、一歩引いて受け止めてみてください。
余裕を持つことで少しは気が楽になるはずです!
期待値と現実のギャップにイライラしている
もう一つ考えられるのは「期待値と現実のギャップにイライラしている」と言う心理です。
上司があなたに対して「このくらいできるだろう」「もうこれくらいは理解しているはず」という期待を抱いている中で、実際に蓋を開けてみるとそのレベルに届いていない。
そんな時に「こんなこともできないの」というセリフを吐いてしまうというわけです。
しかしこれはあなたのせいでもなんでもありません。
大事なのはその“上司の期待はだいたい言語化されていない”ということです。
つまり、あなたに対してきちんと伝えられているわけでもないし、そもそも共有された目標でもないというわけです。
にもかかわらず「なんでこんなこともできないの」と言ってくるのは、かなり理不尽ですよね。
ひろゆきじゃないけど「あなたが勝手に抱いた期待ですよね?」って感じです。笑
つまりあなたの課題じゃないってわけです。
上司が抱いた期待を越えられなかったのは、上司が抱いた期待の設定ミスなだけで、越えられなかったあなたのせいではありません。
また、こういう場合は、越えられた時にプラスというだけで「越えられなかった=マイナス」ということ自体がおかしいですよね。
なので、もしこういった場面にあった際は「どういうレベルを想定していましたか?」と逆に聞いてみるのも手です。
上司が抱いている期待値を見える化してもらうことで、不必要なストレスや衝突を減らすことができます。
あえてプレッシャーをかけてくる作戦
また、中には「意図的にあえてプレッシャーをかけてくる作戦」というケースもあります。
要はあえて厳しくいうことであなたの成長を促してるってわけです。
たとえば、
- 「このままじゃ通用しないぞ」と危機感を煽る
- わざと厳しい要求をして、あなたの限界を引き上げようとする
- 大きな課題を課して、プレッシャーの中で鍛える
といった感じです。
「こんなこともできないの」もその1種って感じですね。
また、こうしたやり方は、昔ながらの指導法として一部の上司に根強く残っています。
もちろん、それが本当にあなたのためを思ってのことか、単なる“しごき”かは見極めが必要ですが、相手が意図的にプレッシャーを作っている可能性は十分にあるかと…!
もしそう感じたら、本当に育成のためなのか、それともただのストレス発散なのかを判別するのが大切です。
ただのストレス発散で言っているだけ
そして最後に忘れてはいけないのが「ただの八つ当たり」です。
要はただのストレス発散ですね。
上司も1人の人間です。
中間管理職としてのプレッシャーや上層部からの要求、家庭での立場など色々とストレスを抱えているはずです。
そんな行き場のないモヤモヤが、立場の弱い部下に向かって出てしまうといったこともあるわけです。
ただ、こうなると上司の言っている内容に意味なんてありません。
あなたのために言っているわけでもなんでもなく、重大なミスを指摘して成長して欲しいわけでもなく「ただの八つ当たり」「ただのストレス発散」というだけです。
こういった時は真正面から受け止めるのは損しかないので「ああ、これはただのストレス発散なんだな」とだけ心の中で思って、感情を切り離しましょう。
もしくはポーズとしてはいはいと聞き入れたり、メモを取るだけ取って、感情的に反応しないというやり方がおすすめです。
こうすることで相手のストレスの矛先にならずに済むわけです。
番外編:「やってみせ言って聞かせてさせて見て褒めてやらねば人は動かじ」by 山本五十六
余談ですが、この言葉聞いたことあるでしょうか。
これは、連合艦隊司令長官・山本五十六が残した、人を動かすためのリーダーの心得を端的に表した言葉です。
要は
- まずは自分が見本を示すこと
- 次に言葉で伝えて理解させること
- そして実際にやらせてみせること
- 最後に努力や成長を認めて誉めること
といったフローで教えることが1番人を動かす上で大事だよってことです。
一方で命令したり「こんなこともできないの」と圧をかけるだけでは人はついてきません。
見本→説明→経験→承認というプロセスを踏むことで、はじめて相手が自発的に動いてもらえるようになります。
ぜひ上司もこの言葉を知って欲しいですよね。笑
逆にあなたが上の立場になった時は、上司から言われた言葉を反面教師にして、この言葉を思い出しながら、教えてあげて欲しいなと思います!
「こんなこともできないの」でメンタルがやられてしまう理由
ここからは「こんなこともできないの」を言われると、なぜメンタルがやられてしまうのかについて解説していきます。
自分がなぜやられてしまうのかといったモヤモヤの正体を言語化することで、ただの感情的な傷から認知の整理に変わっていきます。
となれば受け止め方の選択肢が広がりますし、必要以上に自分を責めなくても済むようになります。
この章では
- 人格を全否定されているような気がする
- 具体的な改善策がなく、また同じようなことが起きそうと思うから
- 「上司=評価者」の破壊力
- 過去の失敗体験がフラッシュバックするから
- 自分ならできるという自己効力感が削られる
といった5つについて1つずつ解説していきます。
人格を全否定されているような気がする
メンタルがやられてしまう理由の1つは「こんなこともできないの」が単なる能力の指摘を超えて“あなたという存在そのもの”を否定されたように感じてしまうからです。
本来、仕事というのは「できる」「できない」という事実しかありませんが「“こんなことも”できないの」という言葉は
- =あなたはダメ人間だ
- 社会人として失格だ/平均以下だ
といったレッテルを貼ってしまう響きを含んでいます。
さらにこの言い方は具体的な改善策の指示は伴っていないため「どうすればいいのかわからない」「ただ責められただけで終わり」という無力感を強めてしまいます。
こういった理由で人界を全否定されたような痛みに直結するわけです。
具体的な改善策がなく、また同じようなことが起きそうと思うから
また具体的な改善策の指示がなく、解決の糸口がないまま責められてしまうのもメンタルがやられてしまう理由の1つです。
その場で「こうすればできるようになるよ」と具体的なアドバイスがあれば、少なくとも次に向けて動いていくことができます。
具体的な指示がないと「また同じようなことが起きて、また怒られてしまうのでは…」と考えてしまいますよね。
これは心理学でいう“学習性無力感”につながっていきます。
つまり「どうせ何をやってもだめだ」と感じてしまい、挑戦意欲や自信が奪われてしまう状態に陥ってしまうというわけです。
これが心がすり減ってしまう大きな理由です。
「上司=評価者」の破壊力
そして「こんなこともできないの」と放つ相手が「上司=評価者」であるという事実もまた、強烈に刺さる理由の1つです。
これがただの同僚や友人であれば「そんな言い方しなくても」と受け流すもできるかもしれませんが、上司は評価者であり、その評価は今後のキャリアに直結していきます。
だからこそ、この言葉は「自分の価値を低く見積もられた」と感じてしまい、重みが増してしまうわけです。
そして具体的な改善策がないことで、こちら側でコントロールしづらいというのも厄介ですよね。
- 「できないと思われたら、昇進やボーナスに響くかもしれない」
- 「失望されたら、この職場での居場所がなくなるかも」
そうした不安が一気に押し寄せて、言葉の破壊力を何倍にも増幅させ、メンタルがやられてしまうわけです。
過去の失敗体験がフラッシュバックするから
この言葉は現在の指摘だけではなく、過去の失敗体験を呼び覚ましてしまいます。
僕も過去に言われた際、学生時代のアルバイトで言われた記憶がぐわっとフラッシュバックしました。笑
要は過去に似たような場面で叱られたり、恥をかいた経験がフラッシュバックしてしまうことが、実際に言われた以上にメンタルをやられてしまう理由です。
理屈では今のこと今のことと分かっていても、身体はあの時の痛みや恐怖を再現してしまい、ただの一言のはずが、過剰なほど辛く響いてしまうというわけです。
自分ならできるという自己効力感が削られる
また「自己効力感が削られる」というのもメンタルがやられてしまう理由の1つです。
自己効力感とは、心理学者バンデューラが提唱した概念のことで「自分ならやれる」「努力すればなんとかなる」という感覚のことを指します。
この感覚があるからこそ、人は挑戦できるし、困難にも立ち向かうことができます。
しかし「こんなこともできないの」という一言は、その根っこを揺るがし
- 「こんなこともできない=お前はダメだ」というレッテルを貼られたように感じる
- 「頑張っても評価されないかも」という無力感に変わる
- 「次もうまくいかないんじゃないか」という予期不安を呼ぶ
結果「自分ならできる」という心の支えが崩れ、挑戦する意欲そのものが下がってしまうというわけです。
「こんなこともできないの」と言われたら受け止め方を変えるしかない
では最後に「こんなこともできないの」と言われた時の対処法を最後に解説していきます。
こんな時代錯誤な言葉を言ってくる相手を変えることができたらベストではありますが、現実的にそれは難しいです。
だからこそ、こちらができる対処法は“受け止め方を変える”だけです。
この章では
- 距離をとって切り離す
- 意味を変えて受け止め直す
- 行動につなげて“成長機会に変える”
3つのSTEPに分けて解説していきます。
距離をとって切り離す
まずは「距離をとって切り離す」です。
- この人は今イライラしているだけ
→相手の感情を自分に向けずに、相手の状態として切り離す - この人はこういう言い方をするタイプと割り切る
→言葉や言い方をその人の癖やスタイルとして受け止めて、自分の攻撃として受け止めない
こうすることで、責められているといった破壊力を軽減することができます。
意味を変えて受け止め直す
次に「意味を変えて受け止め直す」です。
- 事実と感情を分けて捉える
→「できていない」という事実と、「できないことを責められた」という感情を分離して考える。 - 期待値の裏返しと考える
→「できない」ではなく、「もっとできるはず」と思っているからこその言葉と受け止める。 - “今の自分の状況”を思い出す
→新しい環境や学びの途中なら、「できなくて当然」と改めて意識する。
受け止め方・捉え方を変えることで、言われてもダメージが少なくなります。
行動につなげて“成長機会に変える”
最後に「行動に繋げて成長機会に変える」です。
- 改善点だけ拾う
→人格否定の言葉は流し、行動に必要な部分だけ抜き出す。 - 「じゃあ次はどうすればいいですか?」と聞く
→否定をそのまま受け取らず、具体策を引き出すことで成長のきっかけにする。
成長に繋げることで「こんなこともできないの?→成長機会」とパブロフの犬形式で、考えられるようになります。
自分の心が折れる前に逃げよう
ここまで色々と上司の心理やメンタルがやられてしまう理由、受け止め方について書いてきましたが、それでも限界を超えるほど辛い場合は、逃げることも選択肢の1つです。
上司の言葉の受け止め方を工夫することは大切ですが、それは自分の心を守るための手段で我慢を続けるためではありません。
もし毎日のように心がすり減るなら
- 部署異動を願い出る
- 信頼できる上司や人事に相談する
- 転職を視野に入れる
というのも大切です。
逃げるという選択肢を取るとき、“最も現実的で、自分の未来を守る手段が「環境を変えること」”です。
正直、こういった上司を変えるのは簡単ではありません。
人事や相談窓口が動いてくれるとしても時間がかかるし、その間に心が削られてしまうこともあります。
だからこそ「ここから出る」という逃げ道を早めに作っておくのが大切です。
転職・異動の準備は甘えでも敗北でもなければ、逃げでもありません。
むしろ、自分の人生を守るための“前向きな戦略”です!
具体的な準備ステップ
- キャリアの棚卸しをする:これまでの経験やスキル、強みを書き出して、自分がどんな仕事で活躍できるか整理します。
- 異動希望を出す:同じ会社でも部署を変えられるなら、それだけでパワハラから抜け出せるケースもあります。
- 転職市場をチェックする:自分のスキルでどれくらいの求人があるか、年収相場はどうか、情報を集めるだけでも気持ちが軽くなります。
- 転職エージェントに登録する:非公開求人や自分に合う企業の紹介を受けられるだけでなく、履歴書の添削や面接対策もしてもらえるので、効率よく進められます。
転職活動は“逃げ道”を作るだけでも価値がある
今すぐ転職するつもりがなくても、エージェントと話してみるだけで安心感が違います。
「最悪、ここから出られる」という逃げ道があるだけで、今の職場で受けるストレスはかなり和らいでいきます。
もし少しでも転職を考えているなら、まずは情報収集から始めてみるのがおすすめです。
最近は無料で利用できる転職エージェントが多く、大手なら「リクルートエージェント」「doda」「マイナビエージェント」など、あなたの状況に合った求人を一緒に探してくれます。
心が壊れる前に、次の場所を見つけておく。
それが、こういった環境から抜け出すための一番の安全策です。
まとめ:「こんなこともできないの」で心を壊されないために
上司の「こんなこともできないの?」は、マウント・勝手な期待・プレッシャー・八つ当たりなど、上司側の事情によるものが多く、あなたの価値を否定する言葉ではありません。
受け止め方は
- 距離を取って切り離す(相手の感情として捉える)
- 意味を変えて受け止め直す(期待の裏返し・事実だけ拾う)
- 行動につなげる(改善点を質問・成長機会に変える)
それでも辛ければ、異動・相談・転職など環境を変えるのも立派な選択肢の1つです。
メンタルがやられてしまっては、元の通常な状態に戻るのもなかなか難しいです。
あなたは十分頑張っていますし、自分をこれ以上責めなくても大丈夫です。
逃げるのも、環境を変えるのも、自分を守るための立派な選択です。
心が折れる前に、自分を守る行動をとっていきましょう。
また、この記事で、少しでも心が軽くなる方がいたらいいなと思います。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました!